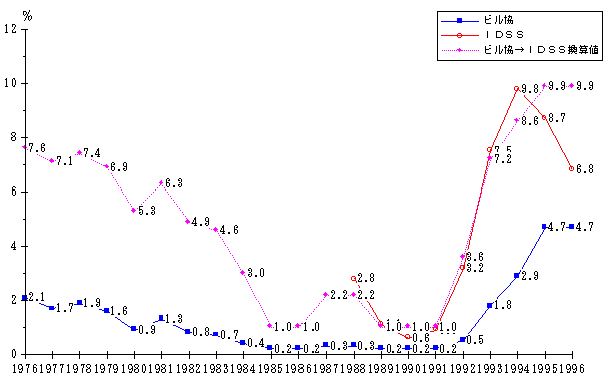
再び来るオフィス不足時代とその対応
(『日本不動産学会会誌No.44』1997)
東北芸術工科大学教授
計画研究所コスモプラン代表
水鳥川 和夫
1.オフィスビル需給の変動とその要因
1985年代後半に絶好調を迎えたオフィスビル市場は、1990年代に入り急激に過剰感が強まり、東京区部のオフィス空室率は、1994年6月に9.8%のピークとなった1)。このまま10%を突破するかに見えたが、その後反転し、1996年9月時点での空室率は6.3%になり、現在は順調に回復しつつある。1990年代当初のこのようなオフィスビルの過剰をもたらした原因は何であったのだろうか。
図1 オフィス空室率の実績(東京区部)
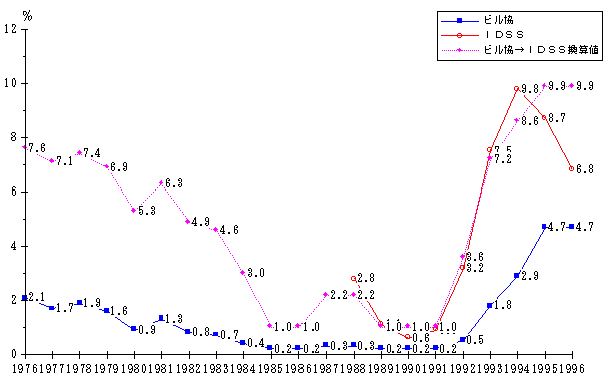
図1には、東京区部における長期的なオフィスビル空室率2)の推移を示してあるが、1984年まで趨勢的に減少してきた空室率は、1985年には1.0%になり、流通在庫のために5%程度の空室率が必要といわれるなかで、空室率が3%を切る状態が8年も続いた。新規に大きなフロアが確保できないため、各社はタコ足状にオフィスを分散せざるを得なかった。
図2 オフィスワーカー年間増加数の推計(東京区部)
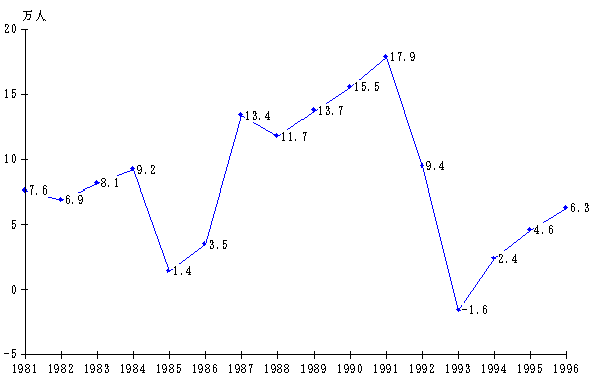
東京区部のオフィスワーカー数の年間増加数の動向をみてみると、円高不況時の1985、1986年に一時的に増加テンポが鈍ったものの、産業全体の頭脳化に伴い、1980年代を通じて増勢を強め、1987〜1991年には、年間13〜18万人の増加となり3)(図2)、オフィスワーカーの純増だけで年間250〜350ha程度の新規オフィス需要をもたらしたと見積もられる。
図3 オフィス着工量の実績(東京区部)
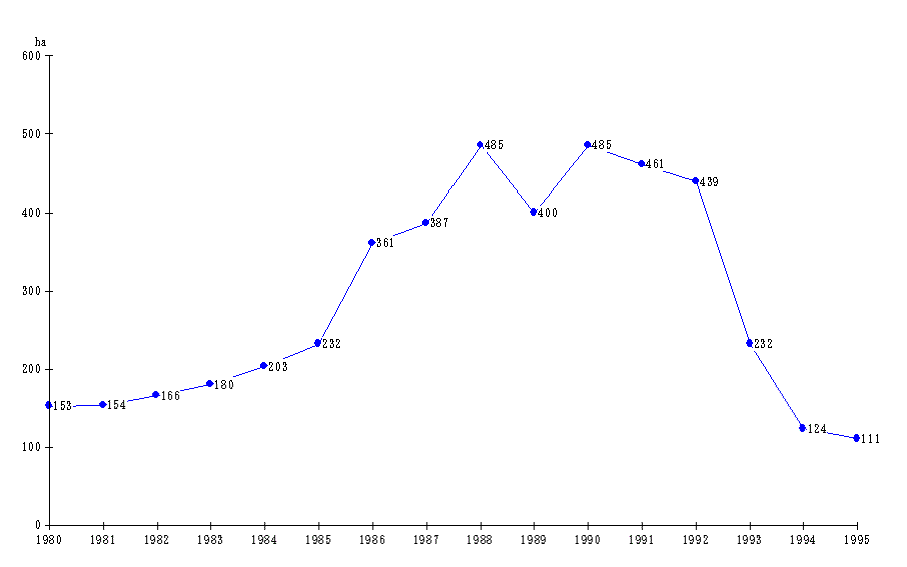
一方、東京都区部におけるオフィス着工量は、1980年代前半には、たかだか150〜200ha程度に止まっていたが、オフィス需要の高まりに対応して、1986年頃からオフィス着工量も増加し、400〜500haとなった(図3)。しかし、それを上回るオフィスワーカー数の増大と1人当たり床面積の増大への要請があり、オフィス空室率は、1991年まで非常に低い水準にあった。この期間は、オフィスの供給が不足しており、これが、地価高騰の一つの要因となったと考えられる。
以上から1980年代後半のオフィスビル建設ラッシュは、オフィスワーカーの増加という実需に基づいたものであり、決してバブリーなものではない。しかし、需給が逼迫してから供給が開始されるまでにかなりの時間遅れが生ずるというオフィス市場の構造的問題があり、これが地価の高騰やその後のオフィス不況を一層深刻なものにしているのである。
1992年以降の経済環境の悪化に伴って、オフィスワーカーの増加数は急減し、1993年にはマイナス1.6万人と純減となった。また、急激な経営の悪化に対処するために、緊急避難として、借りていたオフィスの一部を返し、スシズメにすることもあった。この結果、オフィス需給は、急激に緩み、空室率は1993年央には7.5%と急激に上昇した。
空室率の上昇は、1990年代に入ってからの急激な経済の冷え込み及びこれをもたらした経済政策が原因である。
オフィスワーカーは、1994年からは増加に転じ、1996年(1〜9月までのデータ)では、6.3万人の増加となった。オフィスワーカーのうち専門的・技術的職業の増加が大きく、事務従事者も増加に転じているが、管理的職業は、依然、停滞傾向にある。
近年、オフィス需給が急速に回復してきた理由のもう一つは、予想を超えるオフィス着工面積の急減にある。図3をみると、東京区部のオフィス着工量は、1995年には111haとなり、ピーク時の1/5にまで落ち込んでいる。オフィスが着工されてから実際に市場に出てくるまでには、数年単位の時間がかかるので、着工量のこのような急減は、むしろ近い将来、深刻なオフィス需給の逼迫をもたらすことが懸念される。
図4 1人当たりオフィス床面積の推移(東京区部、推計)
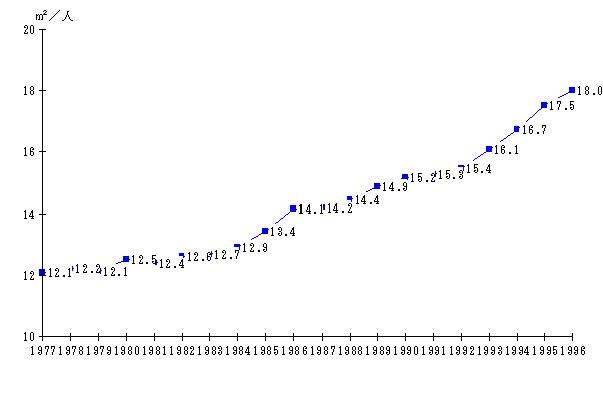
空室率の増大は、オフィス賃貸料の低下をもたらし、また、広いオフィスフロアが確保できる状態となったために、これまで潜在化していた需要が増加してきた。この結果、1人当たりのオフィス床面積も顕著に増加した4)。図4をみると1986年から1992年までは、年間0.22㎡の増加であったものが、1992年から1996年においては、0.65㎡/年と約3倍のテンポで増加している。このような1人当たり床面積の増大も近年のオフィス需要の回復の大きな要因である。
以上を総括してみると、東京都区部において、1990年央から1996年央までに2,200haが供給され、このうちオフィスワーカーの純増により600ha、1人当たり床面積の増加により1,100haが埋まったと考えられる。
2.2001年オフィス市場の予測
では、今後のオフィス需給はどうなるのだろうか。以下では、オフィス需給モデルを作成し、2001年のオフィス市場についての予測を行ってみた。
(1)予測方法
①需要
オフィス需要は、オフィスワーカー数と1人当たり床面積の積である。オフィスワーカー数については、国民総支出等の経済規模とよい相関が認められる。
両者を回帰分析して、以下の予測式が得られる。
OW=480.39+0.0038438GNE (R2=0.98877) ---------- (1)
計測期間:1977〜1996年の20年間
OW:全国オフィスワーカー数(万人)
GNE:国民総支出(10億円)
図5 オフィスワーカー数の実績とGNEによる計算値
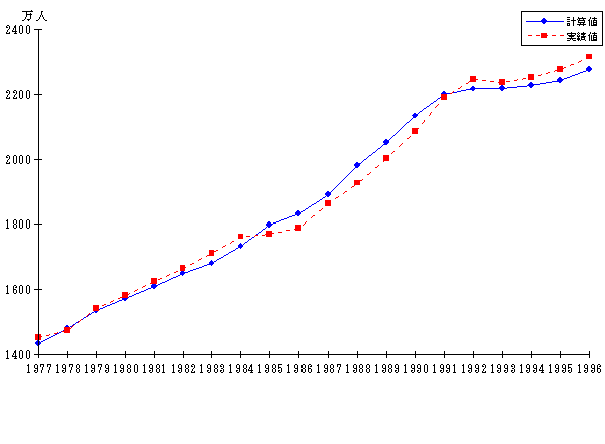
ここで得られたオフィスワーカー数の伸び率を用いて1990年の東京区部のオフィスワーカー数を起点として1991年以降に外挿して将来値を求めた。
一方、一人当たり床面積は、オフィス需給の引き締まりによって、1993年以降の増加テンポ(0.65㎡/年)より低下するであろう。しかし、需給が逼迫していた1986〜1993年の0.22㎡/年よりは上回るであろう。そこで、1996年以降については、0.30㎡/年で増加していくものと仮定した。
②供給
オフィス供給は、着工量に依存する。着工量は、経済状況やオフィス需要によって決まるであろう。しかし、着工までには、開発、設計などの準備を必要とするので、経済状況が悪化しても急には止められないし、需要が回復しても、急には着工できない。これらの要素を勘案して、経済成長率、空室率、前年度着工量の3つの変数により当期の着工量を推計するものとした。回帰式は、
OCi=134.40+9.1599⊿GNEi−17.913VRi+0.66225OCi−1 ----------(2)
(R2= 0.88863)
計測期間:1977〜1995年の19年間
OCi:東京区部当期オフィス着工量(ha)
OCi−1:東京区部前期オフィス着工量(ha)
⊿GNEi:当期国民総支出対前年増加率(%)
VRi:当期東京区部オフィス空室率(%)
1977〜1995年までの実績値と計算値との関連をみると、図6のようになり、オフィス着工の動きを概ね追跡することはできていると考えられる5)。
図6 オフィス着工量の実績値と計算値(東京区部)
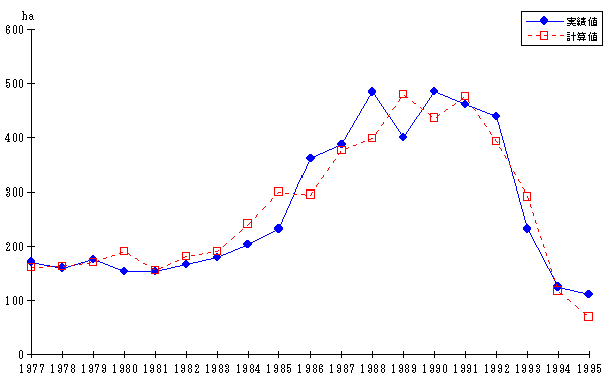
③賃貸料
オフィス賃貸料を決定する要素としては、一般物価上昇率、地価、ビル建設費、金利等が考えられるが、最終的に前期賃貸料と空室率との相関が最も高かった。これから、以下の回帰式が得られる。
ORi=10387−1336.5*VRi+0.86312*ORi−1 (R2= 0.96059) ----------(3)
計測期間:1997〜1996
ORi:東京区部当期オフィス賃料6)(円/3.3㎡)
ORi−1:東京区部前期オフィス賃料(円/3.3㎡)
VRi:東京区部当期オフィス空室率(%)
図7にみるように、この2つの変数だけで、計算値と実績値はかなり一致している。オフィス賃貸料は、結局、前年度の賃料水準と需給関係のみによってほとんどが決まることがわかる。
図7 オフィス賃貸料の実績と計算値
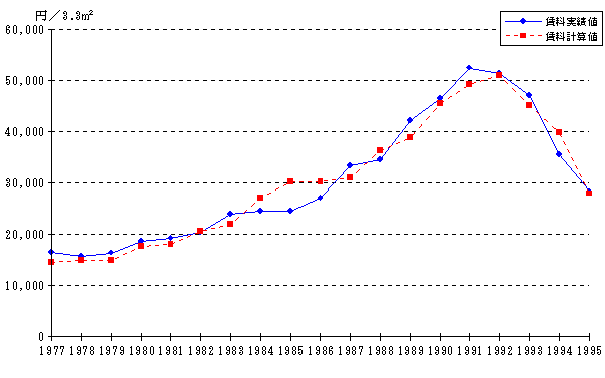
(2)2001年のオフィス市場
経済成長率を与えれば、以上の予測式(1)、(2)を逐次的に解いて、空室率と着工量が得られる。また、式(3)により、空室率から賃貸料が得られる。
①空室率
今後の実質経済成長率が2%の場合、空室率は1996年6月の6.8%から、1997年央には3.9%にまで低下し、1998年央には1.9%にまで低下する。2000年には、マイナス値をとるが、現実にはマイナス値をとることはないので、ゼロに限りなく近い値をとる。このときには、オフィス需給が逼迫して、賃貸料の高騰が起こるであろう。また、成長率が1.5%程度でも空室率は確実に回復し、2001年には0.4%の水準に至る。
図8 オフィス空室率の予測(東京区部)
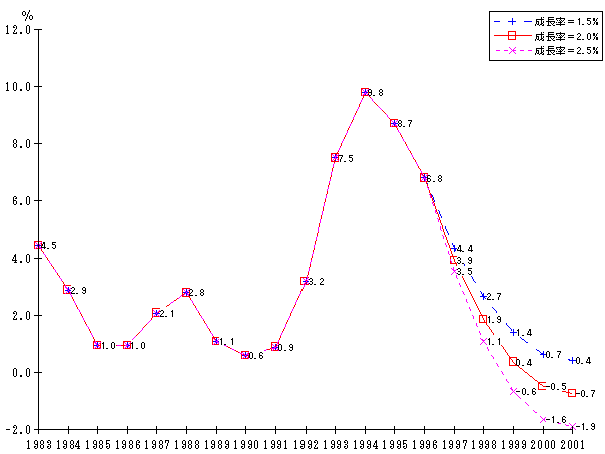
②オフィス賃貸料
オフィス賃貸料は、1991年にピークの3.3㎡当たり5.2万円となった後、1996年央には2.3万円と半分以下の水準
にまで落ち込んでいる。
1996年に底を打ち、1997年には上昇傾向が明確になるだろう。1998年以降、オフィス需給の逼迫により、新規賃貸料は年率10〜15%の上昇となると予想される。なお、このような上昇期には、かつてみられたように、新規賃料と継続賃料の格差が生じ、継続賃料は、これほどは上昇しないであろう。
図9 オフィス賃貸料の予測(東京区部)
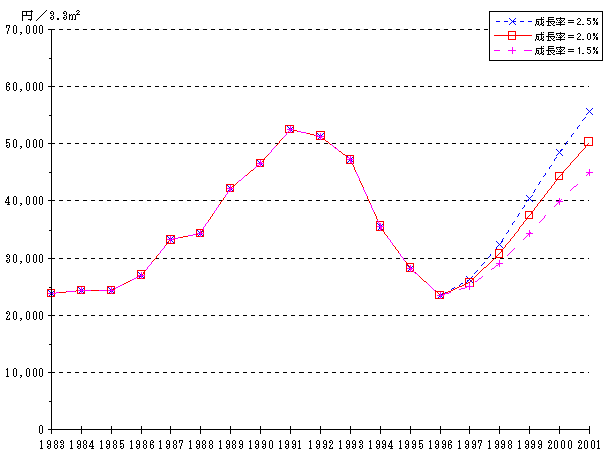
③オフィス着工
オフィス空室率の低下と賃貸料の上昇に対応して、1997年にはオフィス着工もやや上向きになり、2001年には、400ha程度にまで増加する。これは、1988〜1992年年頃のオフィスビル建設ブーム期と同水準であり、大型のオフィスビルを供給しなければ達成できない。これまでストップしていた大崎、品川、臨海副都心などの大型開発が着工もしくは着工予定となっているが、それでもこの400haには不足である。しかし、現状は各社とも新規の大型開発に取り組む状況にはない。1980年代においても、空室率の低下がみられた1982年から、大型オフィスビルの着工が増加し始めた1988年までには、6年のタイムラグがある。この予測どおりに順調にオフィスビルの建設が進むには、かなり困難が予想される。
図10 オフィス着工量の予測(東京区部)
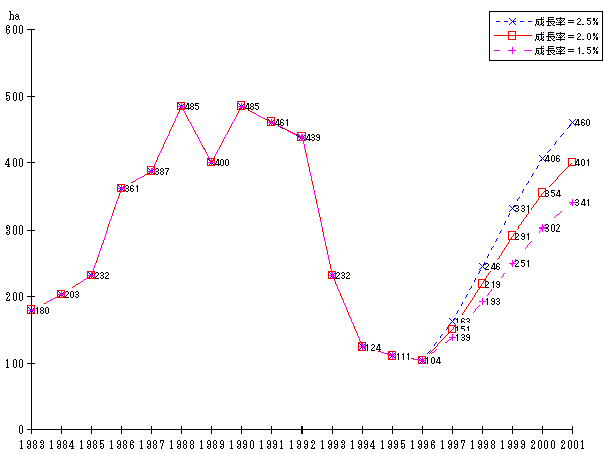
3.業構造の頭脳化とアウトソーシングの影響
以上の予測は、経済成長率2%程度で、オフィスワーカーも年間6〜7万人程度の増加、1人当たり床面積も0.3㎡/年(10年間で3㎡程度)しか伸びないと仮定したうえでの話であり、決して過大な予測をしているわけではない。
これに対して悲観論もある。今後、我が国の経済は、2%程度の経済成長も不可能であり、ゼロまたはマイナス成長が続くとか、大企業は依然余剰のオフィスワーカーを抱えており、今後一層アウトソーシングが進み、オフィスワーカーは、むしろ減少するといった予想である。
確かに、高度成長期の鉄鋼、自動車、1980年代の電子産業などのリーディング産業が見つからないのも確かである。しかし、世界各国における国民1人当たりGNPと労働人口に占めるオフィスワーカーの比率との間には比例関係があり7)、日本は1人当たりGNPに対して、オフィスワーカーの比率は目立って低い。スウェーデン50.9%、イギリス50.0%は別としても、アメリカ46.0%、ドイツ(旧西独地域)46.9%と比較して、日本は34.9%と10ポイントも低い。頭脳化が進まず、肉体労働に依存してきた日本の産業構造が現在の経済的苦境をもたらしている原因ではあるまいか。
さらに、オフィスワーカーを構成する産業構造の違いが指摘される。日本では、法律、会計、マーケティング等の全ての業務を社内でこなそうとしているが、逆にアメリカでは、ほとんどのオフィスワークが外部のビジネス・サービス業に委託されている。政治活動さえもロビイストと呼ばれる法律事務所に委託されていることはよく知られている。これらの産業がオフィスワーカーの大部分を占めているのである。現在、日本でも進みつつある研究開発、設計、会計、法務、特許事務等のアウトソーシングは、オフィス需要を減少させるのではなく、むしろ、オフィスワークの効率化と全国の企業に対するビジネスサービスの拡大を通じて、オフィス需要が拡大していく要因である。
1980年代のオフィス需要の最も大くを占めていたソフトウエア業も、従来社内で抱えていたコンピュータ部門の外部化により急成長がもたらされた。正社員は減っても人材派遣への依存度が高まれば、オフィス需要は減らない。
未だ統計データが出ていないので、実証することはできないが、副都心周辺の新規大型ビルを埋めているのは、NTT及びその関連企業やアップル、サン等の内外の情報通信関連産業群であり、このあとを法律、会計、弁理士事務所等のビジネスサービス業が埋めているのが目立つ。アウトソーシングを通じて新たなオフィス型産業が成長しているのである。
4.適正なオフィス市場の形成に向けて
(1)経済政策の対象としてのオフィス
1980年代を通じた産業構造の変化によって、オフィス市場の規模は全く変わってしまった。東京区部のオフィス床面積の総量は、1980年から1996年の16年間で3,300haから7,000haへと2.2倍の規模に達した。
この結果、経済に及ぼす影響も巨大なものになっている。東京区部だけでも、オフィス投資は、ピーク時年間1.9兆円(1993年)と見積もられるが、それが、4千億円(1994年)に低下し、1兆5千億円の縮小をもたらした。全国では、およそ6.2兆円(1991年)から1.9兆円(1995年)へと4.3兆円の縮小となった。この変動だけでもGNPを1%を減少させたが、乗数効果を考慮するとこの影響は一層大きい。今回の長期不況がいわばオフィス不況でもあることがわかる。
また、バブル経済の発生が超低金利や輸出超過に伴う外貨の流入等金融的側面のみに偏って語られているが、オフィスの供給不足という実需的要因に起因して地価の高騰がもたらされたことを重視する必要がある。
以上のように経済に占めるオフィス投資の役割は極めて大きい。オフィス政策は、単に都市計画上の問題ではなく、住宅投資と並ぶ経済上の問題でもある。したがって、このような大きな変動が起きないように適切に誘導していくことが経済政策の課題としなければならない。
(2)都市開発の安定的な推進
大型のオフィスビルの建設には、通常、数年単位の長期間を要し、開発から竣工まで10年以上を要することも希ではない。このうち半分程度以上の期間は、行政との折衝に費やされる。また、大型の都市開発では、道路、上下水道等の公共投資の先行が必要である。このオフィス開発に伴うタイムラグが、需給逼迫期には地価の高騰などを激化し、また、需給緩和期には、オフィス不況をより大きなものにしてきた。
官民の折衝過程を透明かつ迅速にし、この時間遅れを最小化していかなければならない。
また、インフラ整備を伴う大型の都市開発は、短期的な経済環境にとらわれずに、計画的かつ安定的に推進していくことが重要である。需給が逼迫して、短期間に供給を増やそうとしても間に合わないからである。
近年の政策動向をみると、オフィス=性悪説が主流を占めているようだが、むしろオフィスの過小供給が地価の高騰を招いたように、これを適切に供給誘導していくことこそが重要である。
(3)工業用地等の土地利用規制の迅速な見直し
東京都心部には、オフィスの供給余力がほとんど残されていない。表1は、東京都心3区におけるオフィスビルの建築可能な余裕床面積を推計したものである。千代田区では、既に容積率限度まで建てられており、中央区で600ha弱、港区の内陸部は、住居系の用途地域が指定され大型のオフィス開発はできない。港区の臨海部には広大な土地が存在するが、それでも700ha弱の余力しかなく、都心3区には、合計して1,200ha程度の余裕床面積しかない。これは2001年頃の需要の3年分をまかなうほどでしかないが、この程度を供給するにも、土地の共同利用など再開発が必要な土地が多く、数十年の期間を要するだろう。東京都心3区外には、住居系の用途地域指定が広がっており、業務系用途地域指定はわずかである。これらの住居系地域を再開発してオフィスを供給することは、オフィスの立地条件からも困難である。
東京湾臨海部の鉄鋼業、石油関連産業などは、設備の稼働状況から見て、30%程度の土地が遊休化していると見込まれる(表2)。しかし、これらの土地は、工業専用地域や臨港地区が指定されていたりして、オフィス単独では建設することが可能であっても、オフィスを支える様々なサービスを含めた都市的土地利用を進めることは困難である。これらの土地利用規制の見直しには、10年以上は確実にかかるものと見込まれ、それでも確実に見直しされるかどうか予想がつかないものが多い。これは、実態に合わせて土地利用規制を見直しする行政手続きが整っていないことに起因している。早急に土地利用規制を見直しする行政システムを整備し、新たな業務地区開発に着手する必要がある。
表1 東京都心3区における業務系用途地域余裕容積(平成7年)
|
1)港区の業務系宅地面積及び指定平均容積率は、図上計測による。
2)港区の業務系の建物利用面積は、全面積から東京都『東京都市白書』(平成8年3月、P.42)に
よる港区の住宅地平均利用容積率('91)を住宅系用途地域面積に乗じた数値を控除。
表2 東京湾臨海部における潜在的遊休地の推計
(単位:ha)
|
注)設備稼働率及び面積当たり従業者原単位から推計。
1)生駒データサービスシステム(IDSS)による。
2)IDSSは、1988年からのデータしか利用できない。ビル協(日本ビルヂング協会連合会『ビル実態調査のまとめ』、各年版。各年4月現在。)は、1970年代からのデータが利用できるものの、都心部の優良ビルに偏っているといわれている。両者を比較すると、ビル協の空室率はIDSSよりも一貫して低く、上昇、下降の動きもIDSSの方が早い。IDSSの方が東京区部全体の実勢をよりよく表していると考えられる。そこで、以下のようにビル協の空室率をIDSSのベースに換算して、利用するものとした。
ISDD=5.5633+ 6.4702*LOG(BILKYO) (R2= 0.96078)
ISDD:生駒データサービスシステムベースによる東京区部空室率(%)
BILKYO:ビル協による東京地区空室率(%)
3)オフィスワーカー数は、5年ごとに行われる国勢調査における従業値ベースの職業別就業者数によって確定数が求められるが、1995年国勢調査の結果はまだ出ていない。そこで、総務庁統計局「就業構造基本調査」の全国値の速報を使い、東京区部のオフィスワーカーの伸び率が全国と同様として、1990年を起点として1995年までの各年値を外挿して求めた。また、1990年以前の各年値についても、同様にして補完した。
4)上記3)で求めた各年別のオフィスワーカー数とオフィス床面積、空室率から、1人当たりの床面積を逆算して推計。
5)着工された時点と実際に供給された時点にはタイムラグがあり、大型ビル、小型ビルの構成比等に影響される。ここでは、以下の式を用いて供給量に換算した。
当期供給量=0.8*(0.6*当期着工量+0.3*前期着工量+0.1*前々期着工量)
6)東京区部のオフィスの新規賃貸料については、ビル協のデータとIDSSのデータが利用できる。IDSSについては、1988年以降のもの(Ⅰ)と、それ以前の指数系列(Ⅱ)があり、両者を1989年で接続すると、ビル協のデータとほぼ一致する。
ビル協:日本ビルヂング協会連合会『ビル実態調査のまとめ』、各年版。各年4月現在。実質賃料ベース。保証金金利は、1986年以前は10%、1987年以降は長期プライムレート+0.5%で換算したもの。
IDSS(Ⅰ):生駒商事『IDSS OFFICE MARKET REPORT』'90〜'95、各前年9月〜8月までの新規募集ビルの平均値。実質賃料。
IDSS(Ⅱ):生駒データサービスシステム『'92 IDSS OFFICE MARKET REPORT TOKYO』'92.1.1、P6
7)水鳥川和夫「21世紀に向けてのオフィス需要」『住まいとまち』NO.46,1994.2